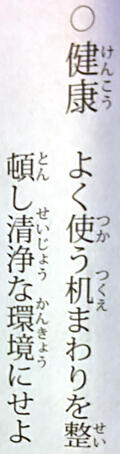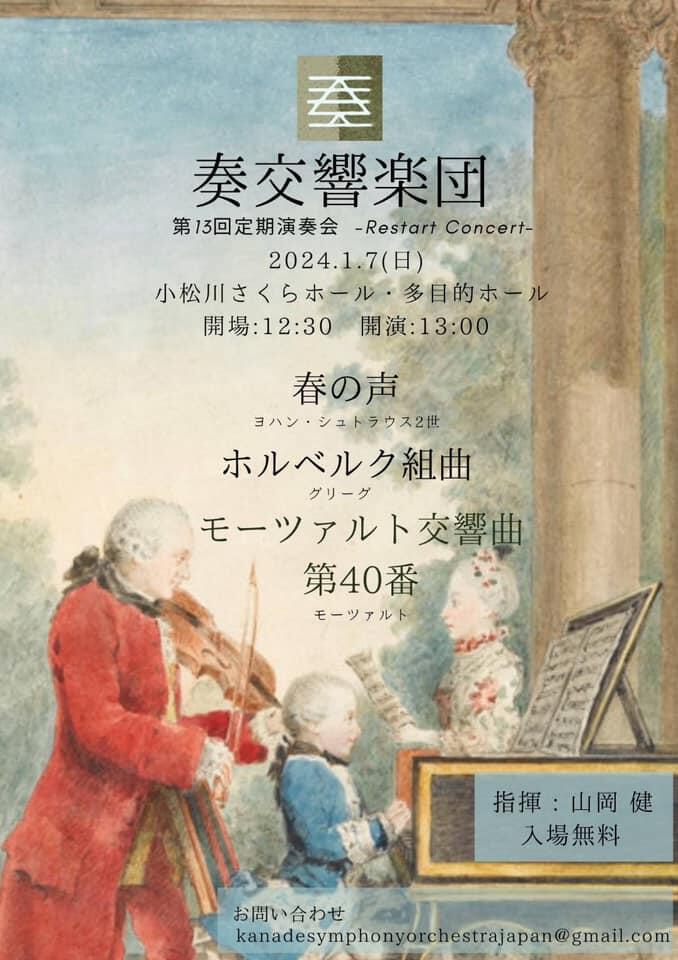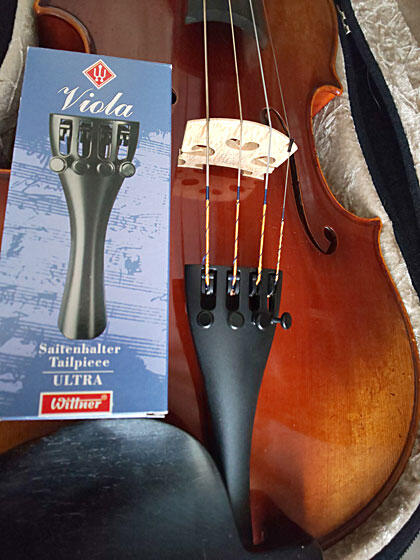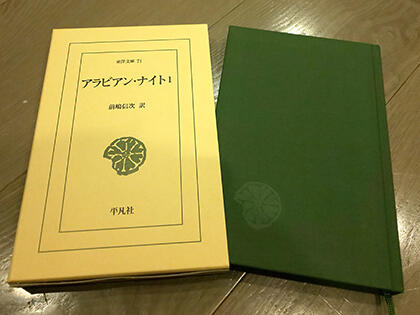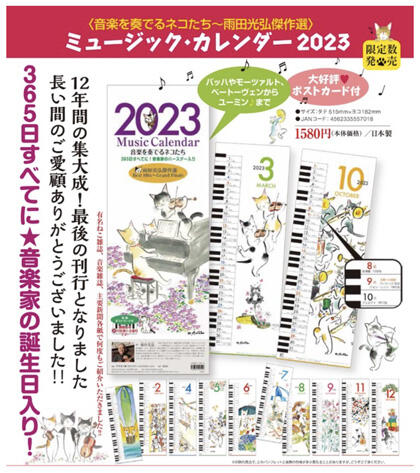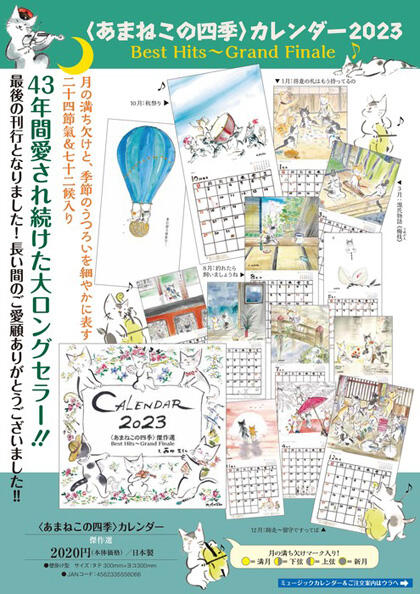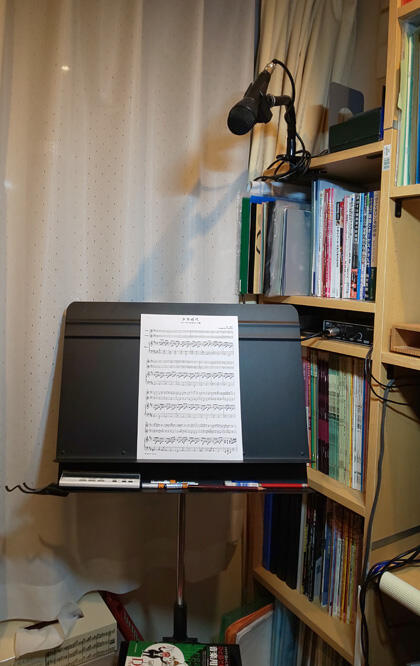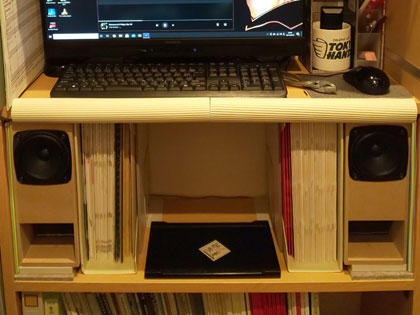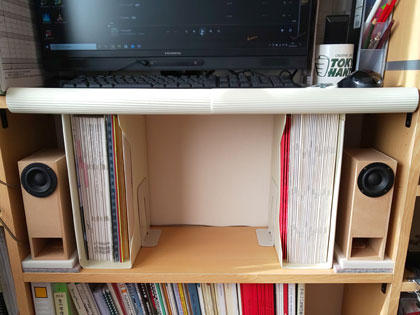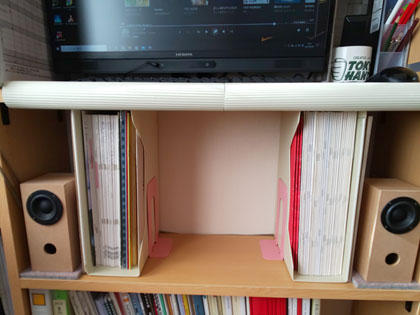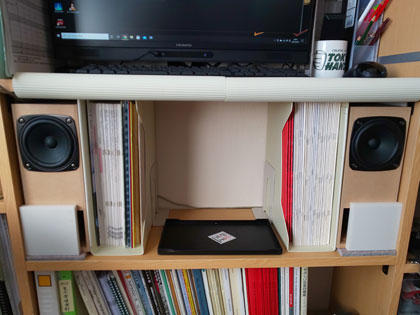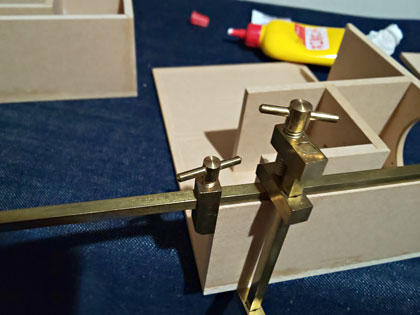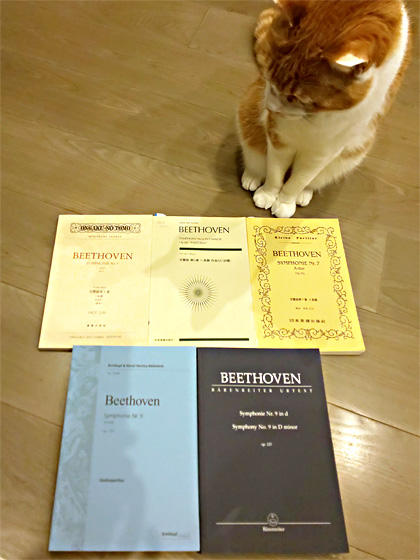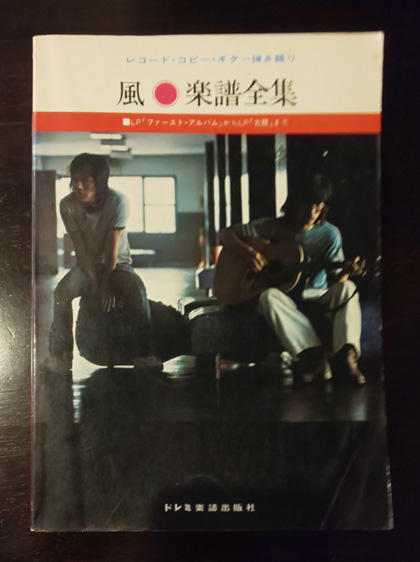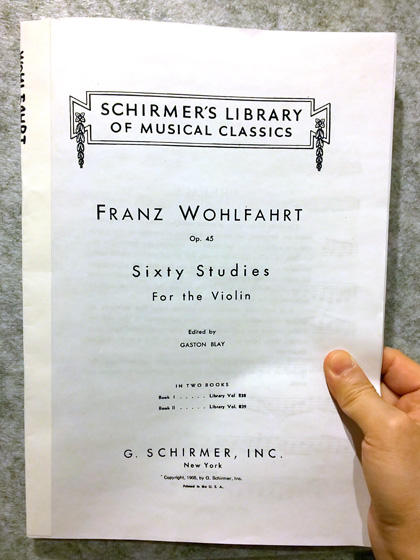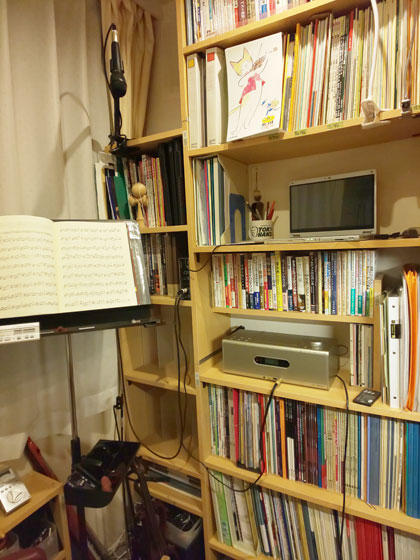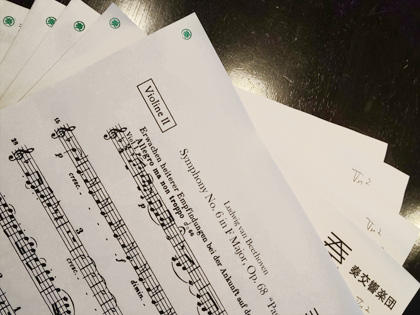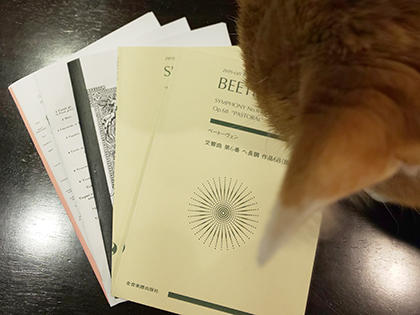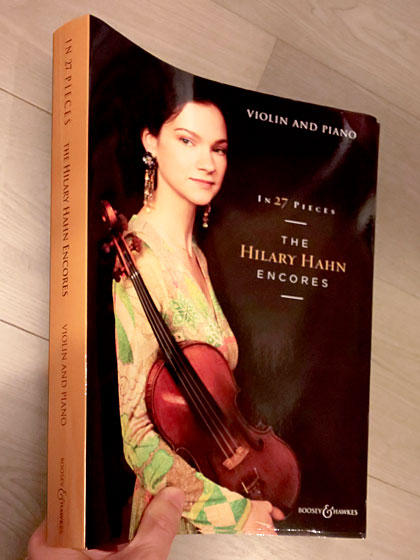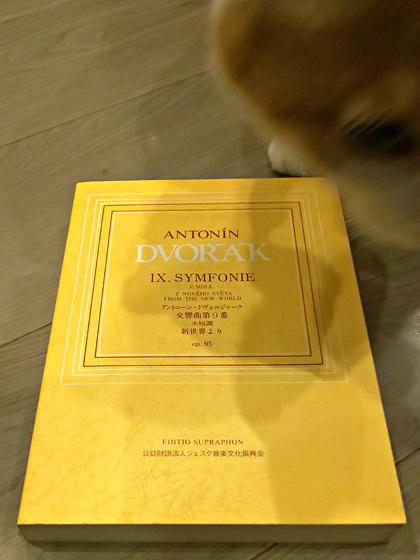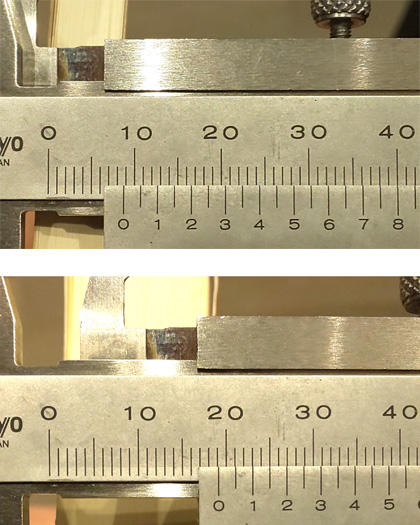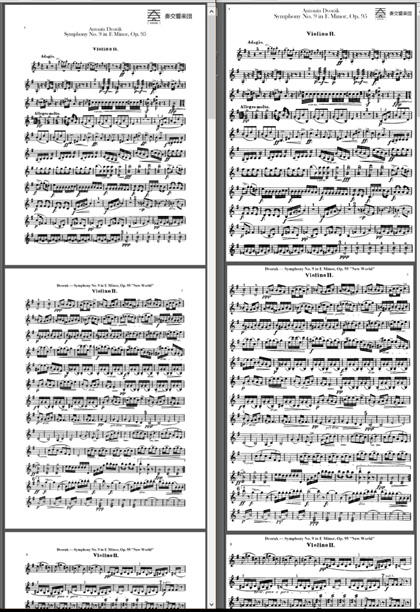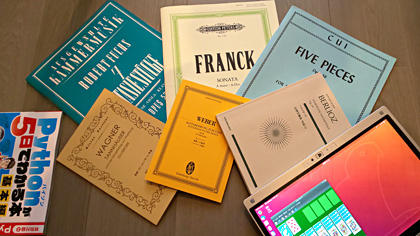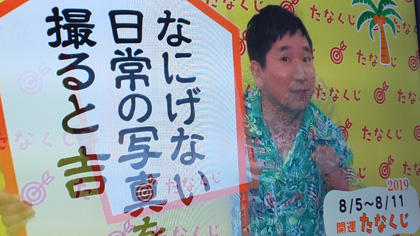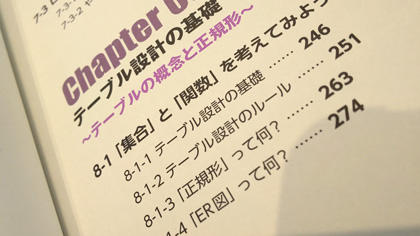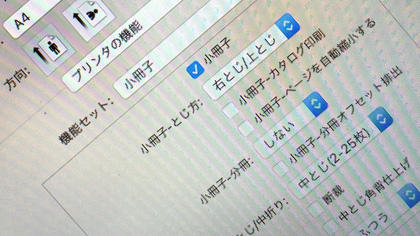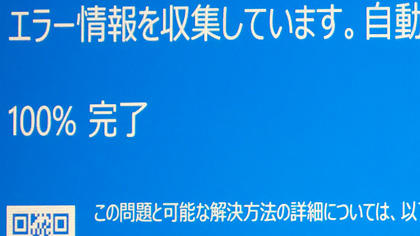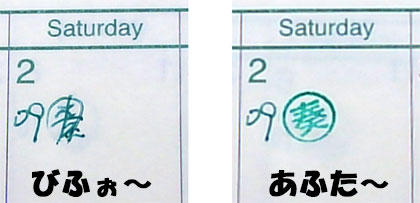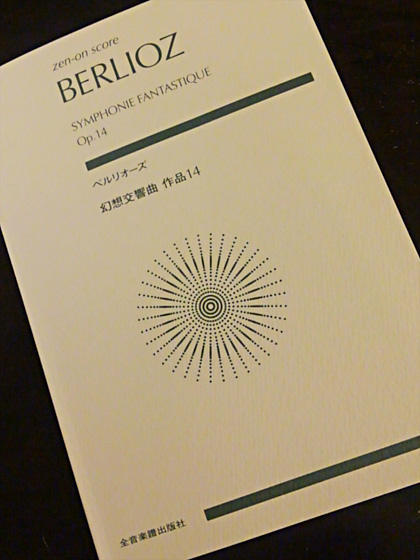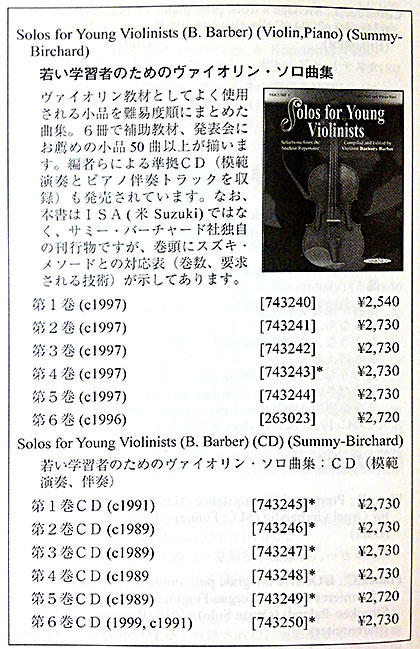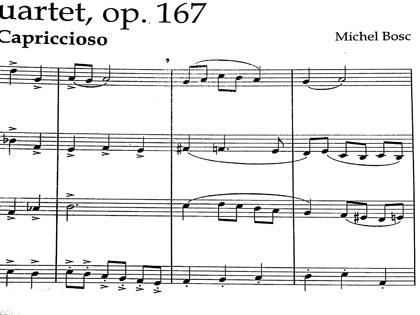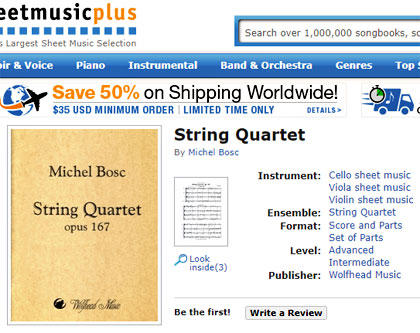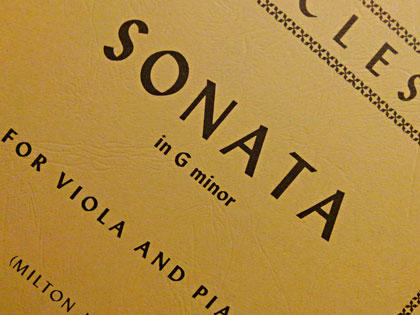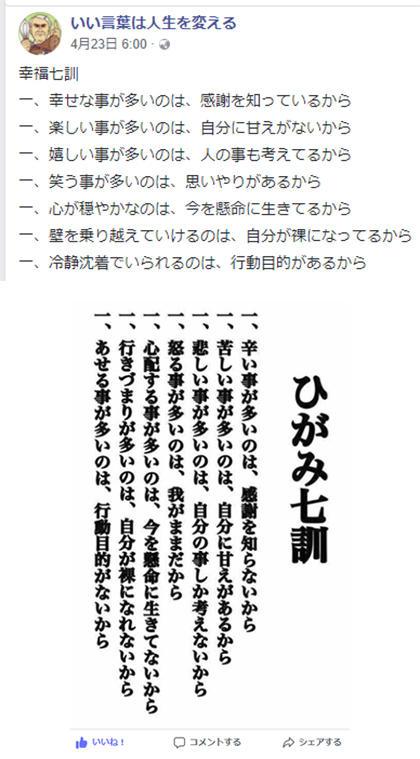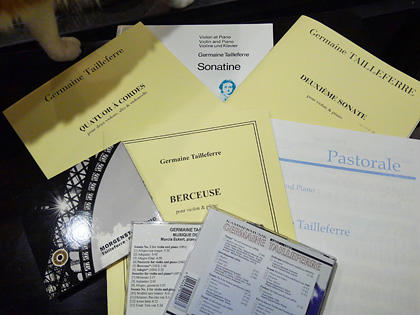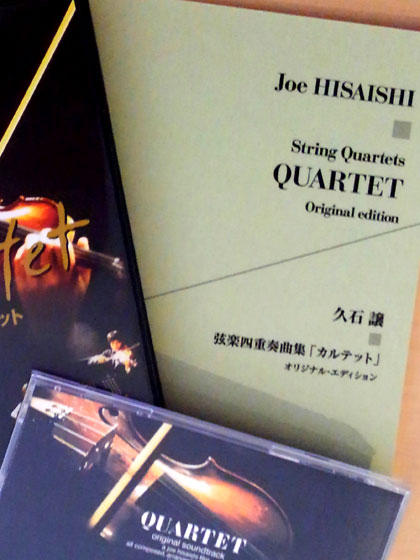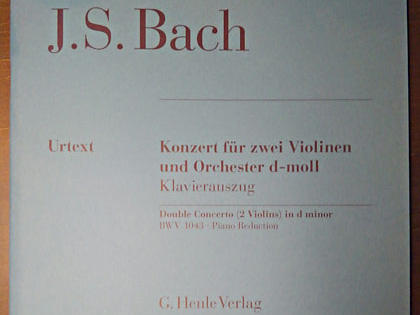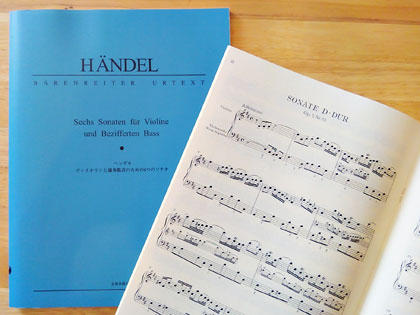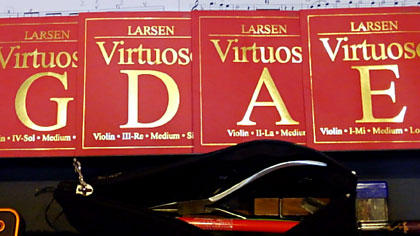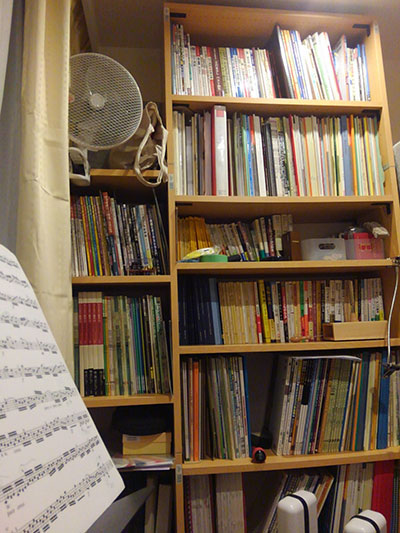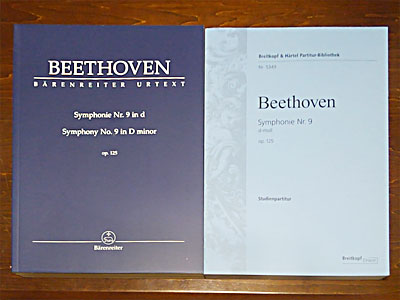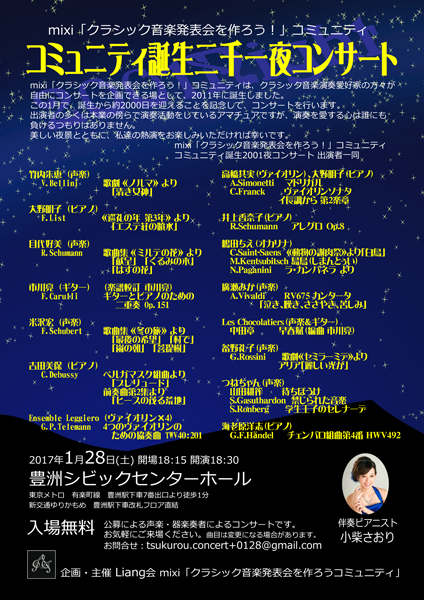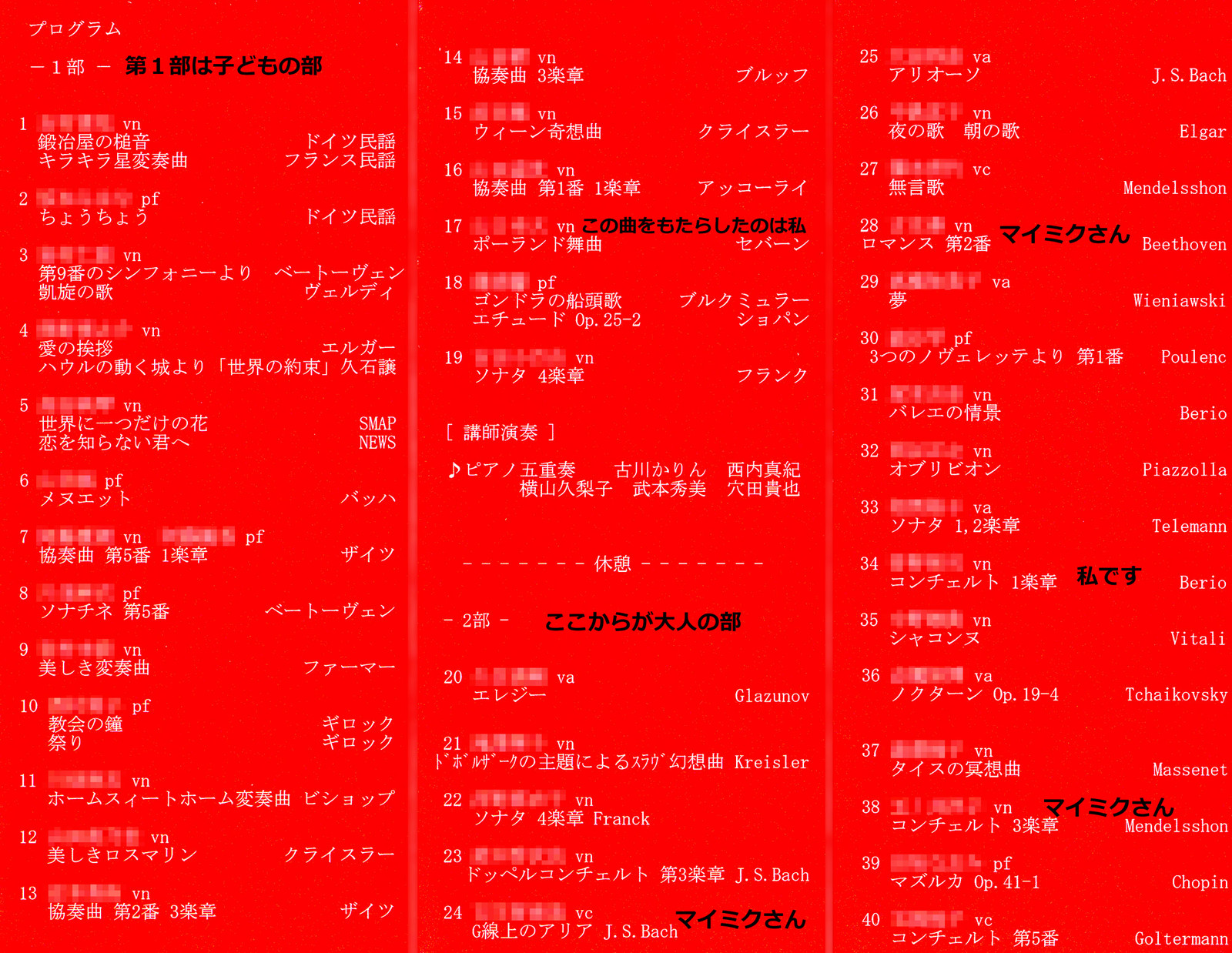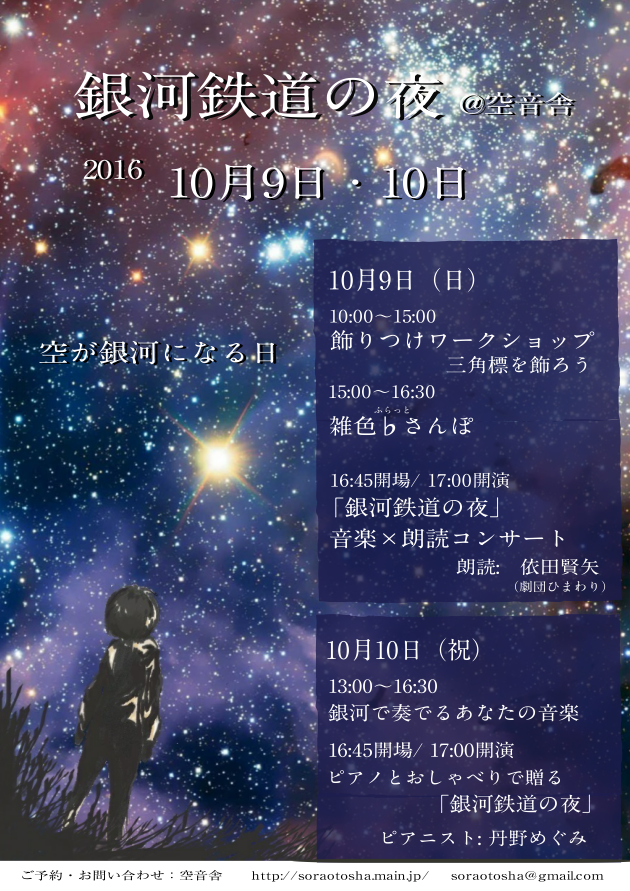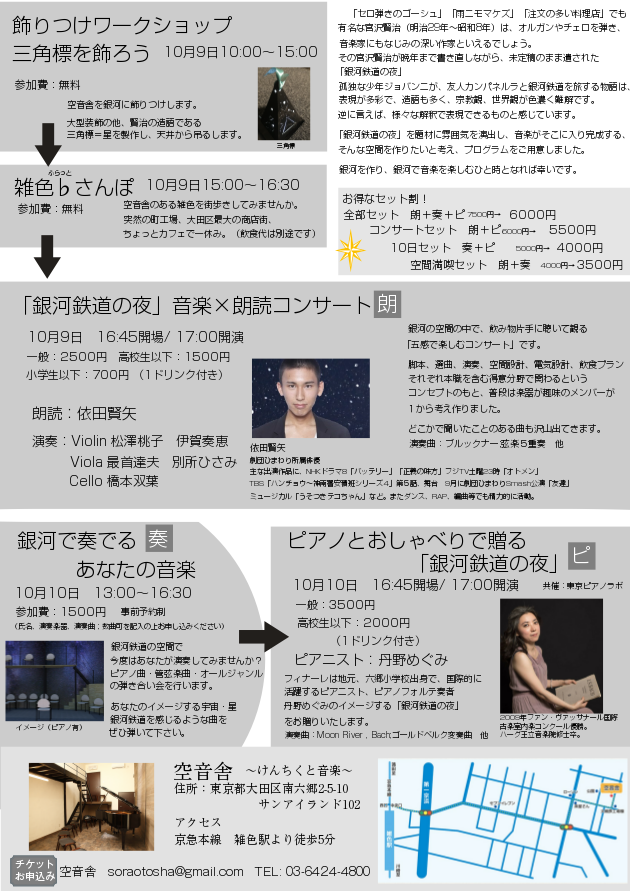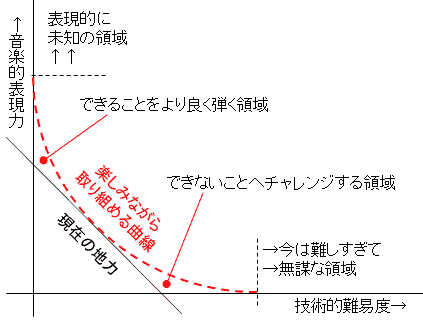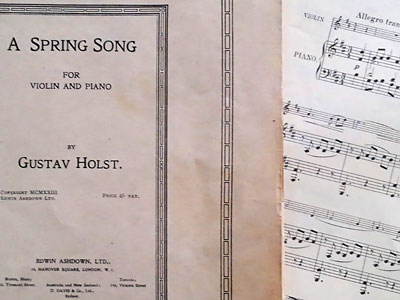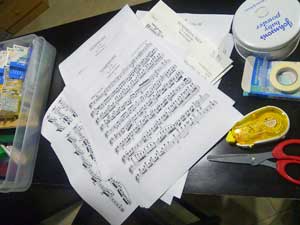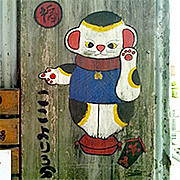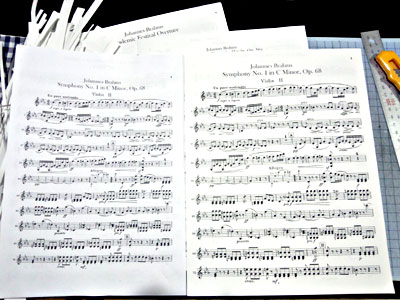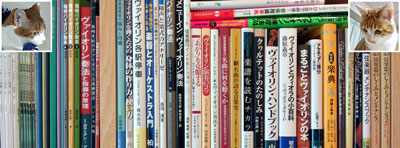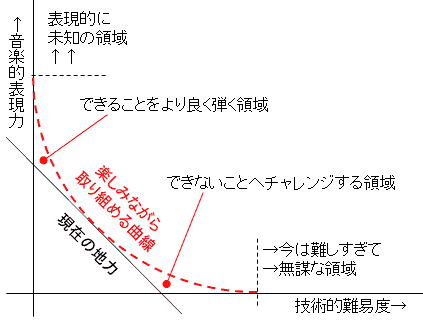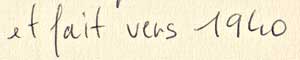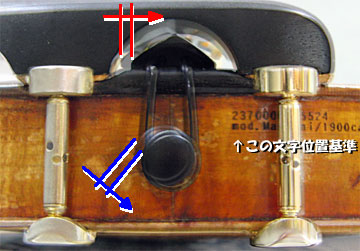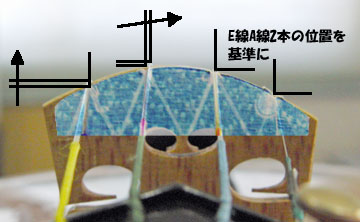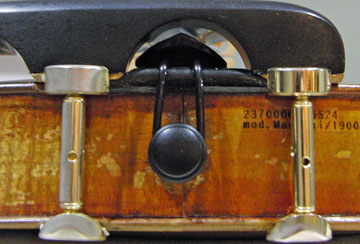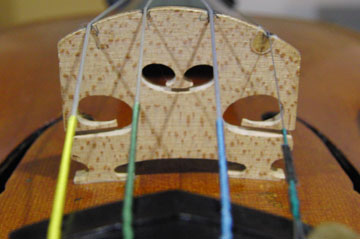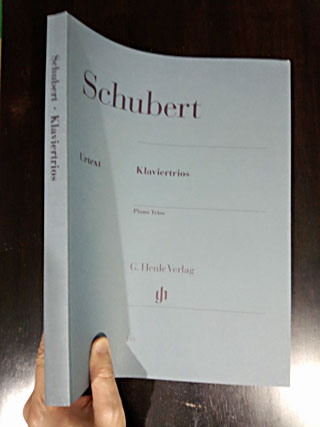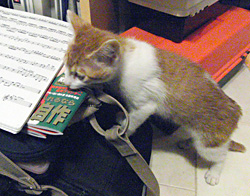2018年全体の振り返り
★発表会、発表会形式の練習会
3月4日(日)初春の演奏練習会@GGサロンホール
mixiコミュ「Concerts for Week-end players」
・ヘンデル/ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調 HWV371(作品1-13)。
第1、第2楽章
3月24日(土)TPGOアンサンブル会@幡ヶ谷KMアートホール
・プレイエル/バイオリン二重奏 Op.48 第2番
4月1日(日)桜の演奏練習会@GGサロンホール
mixiコミュ「Concerts for Week-end players」
・ヘンデル/ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調 HWV371(作品1-13)。
第3、第4楽章
4月21日(土) 合同練習会@杉並公会堂
mixiコミュ「クラシック音楽発表会を作ろう!」
・ヘンデル/ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調 HWV371(作品1-13)。
第1、第2、第3楽章
6月10日(日)初夏の弾き合い会@表参道クラシックスペース(OCS)
・ヘンデル/ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調 HWV371(作品1-13)。
7月1日(日)2ndSounds発表会(ヴィオラ)@空音舎
・ケンタッキーの我が家 ヴァイオリンさんとのデュオ
・バッハ アリオーソ ピアノさんとのデュオ
・ハイドンのメヌエット(初心者用アンサンブル曲集からで詳細不明)
バイオリンさん、チェロさんとのトリオ
9月2日(日)CLARA MUSIK 発表会@鳩ケ谷駅市民センター
・マスネ タイスの瞑想曲
9月8日(土)合同練習会@杉並公会堂
mixiコミュ「クラシック音楽発表会を作ろう!」
・マスネ タイスの瞑想曲
10月27日(土)弾き合い会・2018年秋@OCS
・服部隆之 真田丸
11月4日(日)教室発表会@南大塚ホール
・服部隆之 真田丸
11月23日(金祝)日々の勤労に感謝して演奏を楽しむ会@リリカアートスクール
mixiコミュ「Concerts for Week-end players」
・シューベルト ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第1番 D384
第1楽章
12月30日(日)町工場で弾き・聴き納め会@興和塗装工場
・シューベルト 弦楽三重奏曲変ロ長調D.471
★セミナー等
1月6日(土)OCS室内楽レッスン(ダブルカルテット)
題材:ハイドンSQ Op.1-1
1月14日(日)ストリングスクリニック@空音舎
題材:ヘンデル ソナタ第4番
1月28日(日)OCS室内楽レッスン(ダブルカルテット)
題材:モーツァルトSQ第1番
4月8日(日)OCS松井先生の「響き」を聴く!(ダブルカルテット)
題材:モーツァルト アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
8月19日(日)OCS松井先生の「響き」を聴く!(ダブルカルテット)
題材:モーツァルトSQ第3番2楽章
11月25日(日)ストリングスクリニック@空音舎
題材:タイスの瞑想曲
★OCS室内楽倶楽部「落ちてもいいよ!譜読み会」
・1月6日(土)モーツァルト ディヴェルティメントK136
・2月24日(土)ハイドン「ひばり」1&2楽章
・7月16日(月)落ちてもいいよ!Op3-5の3&4楽章
★ばよ友自習会
mixiコミュ「ばよ友「バイオリン自習友の会」」
6回くらい参加しました。
印象に残っているのは、ピアソラのオブリビオン。
★自分主催のイベント
8月12日(日)エックレスのソナタ会
★演奏じゃないけど
4月7日 (土) C's Ensemble演奏会@大倉山記念館ホール
・ステージセッティングのお手伝いをしました。
以上、何とか今年中にと急いで書いているので、抜けや間違いありそうです。
お気づきのところがありましたら、教えてくださいm(_ _)m
*****
年初に「本番は昨年の教室の発表会のようであるべし。」と掲げました。
事前に迷いや恐れや見栄(^^;を吹っ切って、本番では思うがままの思い切った演奏ができるように。
毎回の本番で、その吹っ切れた段階に至るような準備ができるようになりたい・・・と書きました。
今年は、やや不完全燃焼なところがあったかな、と思います。
それが、同じく年初に書いた
> 本番で「楽しい」と思えるレベルが上がってしまいました(笑)
ということならば良いのですが。
特に今年の後半は、
・6月下旬から8月半ばにかけての喘息悪化
・9月下旬からのカミさん入院
・10月中旬の網膜裂孔
・11月下旬からの左肩神経障害性疼痛
があって、2ndSoundsやOCS室内楽倶楽部をお休みさせていただきながら、曲を
・マスネ タイスの瞑想曲
・服部隆之 真田丸
に絞って、参加できるタイミングで弾かせていただきました。
12月、あるベテランの方から
「SLANさんは、仮に音楽から離れても、いつでも戻れるというふうになったのではないですか」
と言っていただき、あ、ほんとにそうかも、と思いました。
言ってくださった方はじめ、そういう方々が周りにたくさんいらっしゃるからですね。
今年1年、弾いてるときは、いつでも、どこでも、楽しかったです(^^)
ありがとうございました。
P.S.
紅白歌合戦、MISIAに思わず泣いてしまいそうでした。
同じ声圧は保ちながら、切ない時に切ない声質、嬉しい時に嬉しい声質、そこに気が付いたとたんに、歌に捕まってしまいました。